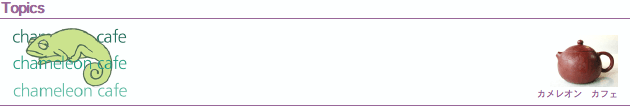ギフトショー出展

さる2月3日~6日、ビッグサイトでの東京インターナショナルギフトショーに出展。といっても、デザイン系を強化したいという運営主体のビジネスガイド社から、インダストリアルデザイナー協会(JIDA)に提供された2コマのうちの極小スペース。ギフトショーは毎年春と秋に開催されるパーソナルギフトの見本市。出展は東館、西館あわせ2400社あまり。デパート、量販、専門店など小売店、通販などのバイヤーを中心に春秋で40万人が訪れるとのこと。 生活用品、文具、ガーデニング用品、ファッション、そして地場産業の産品、JAPANデザイン関連などギフトになりそうなものなら何でもあり。実態は雑貨、ガジェットの見本市。大企業なし、ほとんどがスモールビジネス。でもインテリアスタイル展や100%デザインみたいに気取ってないところが好ましい。また、スモールゆえの意気込み、パワーが感じられることが魅力で、優れた企画、高いデザインレベルのところも少なくない。というわけで品目は多岐にわたり、マジメに見ていてはとても一日では無理。JIDAの出展者は関西ブロックからの参加も含め13名(社)。4日間の会期中2日間、計5~6時間ほどJIDAブースに居りましたが、さまざまな業容の小売業バイヤー、メーカー、企業の新規事業担当の方などと出会いました。ひと口に小売業と言ってもいろいろなビジネスモデルがあるものだといい勉強でした。デザイナー自身がバイヤーと接する機会はほとんどないといってよく、いただいた率直な意見は今後の企画やデザインに生かしたいですね。